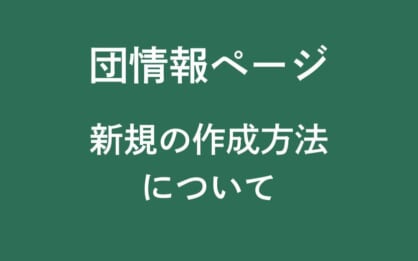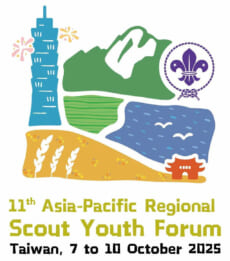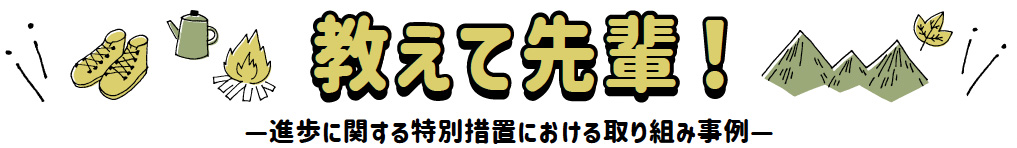
本誌では、コロナ禍によりスカウト活動への支障がある中でも、進歩に関する特別措置を活用しながら、個人の進歩に向けて取り組んでいるスカウトを紹介してきました。今号では、活動自粛期間中とその後の期間をうまく使い分けて活動してきたスカウトをご紹介します。

1. 自己紹介(自身のスカウトの取り組みや学業への取り組みについて教えてください)
高橋 理子(たかはし りこ)さん
今回の進級への取り組みを経て、自分には実践力があることに気がつきました。私は元々やるべきことにうまく優先順位をつけられず、すぐ行動に移すことが苦手だったのですが、今回の進級に向けた活動においては、やると決めたことに最後まできちんと取り組むことができました。スカウト活動以外では、小学校教諭と特別支援学校教諭の免許を取得するために勉強する傍ら、放課後児童クラブの先生をしています。2. コロナ禍で出てきた課題をいかにして切り抜けられたのか教えてください
ベンチャー隊に上進してから、県連盟の集会や日本スカウトジャンボリーに参加したことで県内外のスカウトとの繋がりができ、全国にスカウト仲間がいるというボーイスカウトならではの楽しさに気づくことができました。もっと多くのスカウトに出会いたいと思い、より積極的に集会に参加するようになりました。コロナ禍になり、単独キャンプの実施場所を探していた最中で緊急事態宣言が出てしまい、キャンプ場が利用できなくなってしまいました。日ごろから学校の中でもスカウト活動の話をしていたため、高校時代の友達のツテで寺院の境内をお借りし、そこをベースにキャンプをすることができました。日ごろのスカウト仲間や学校の友達との交流が、自分の活動を助けてくれていると感じました。3. この期間で得たことや成長したこと、今後やりたいことを教えてください
 2020年の全国スカウトフォーラムに、岡山連盟の代表として参加させてもらい、全国のスカウトから多くの刺激をもらいました。事後に県連盟で行ったアフターフォーラムでは、県内のゴミ問題について県内のスカウトで取り組むことになりました。その中で、河川に影響を与える自然物や人工物のゴミがこんなにもあるのか、ということが自分自身の関心に繋がり、個人プロジェクトで取り組みたいと思うようになりました。
活動エリアが水辺に恵まれていたこともあり、カヌーを使って目的地まで行くことをひとつの目的としていましたが、近年の大雨や多くのゴミによって河川でカヌーを使った活動をすることに制限があると分かったことと、度重なる活動自粛により、プロジェクトの計画も変更を余儀なくされました。それでも活動を続けることができたのは、全国や県連盟のフォーラムで出会った仲間との約束や、指導を続けてくれている指導者の支えと励ましがあったからだと思います。
2020年の全国スカウトフォーラムに、岡山連盟の代表として参加させてもらい、全国のスカウトから多くの刺激をもらいました。事後に県連盟で行ったアフターフォーラムでは、県内のゴミ問題について県内のスカウトで取り組むことになりました。その中で、河川に影響を与える自然物や人工物のゴミがこんなにもあるのか、ということが自分自身の関心に繋がり、個人プロジェクトで取り組みたいと思うようになりました。
活動エリアが水辺に恵まれていたこともあり、カヌーを使って目的地まで行くことをひとつの目的としていましたが、近年の大雨や多くのゴミによって河川でカヌーを使った活動をすることに制限があると分かったことと、度重なる活動自粛により、プロジェクトの計画も変更を余儀なくされました。それでも活動を続けることができたのは、全国や県連盟のフォーラムで出会った仲間との約束や、指導を続けてくれている指導者の支えと励ましがあったからだと思います。
 「自粛期間中でもできることはきっとある」、そう自分に言い聞かせて、ゴミが堆積しているエリアを自分の足で確認して回り、カヌーの利用が再開されてからは活動範囲を拡げ、自分だけでなく後輩スカウトも楽しくカヌーなどの水辺のプログラムに挑戦できるように、水辺のゴミ回収や回収できない大型の漂流物の堆積場所の調査などを行い、形を変えながらもプロジェクトを完遂することができました。
「自粛期間中でもできることはきっとある」、そう自分に言い聞かせて、ゴミが堆積しているエリアを自分の足で確認して回り、カヌーの利用が再開されてからは活動範囲を拡げ、自分だけでなく後輩スカウトも楽しくカヌーなどの水辺のプログラムに挑戦できるように、水辺のゴミ回収や回収できない大型の漂流物の堆積場所の調査などを行い、形を変えながらもプロジェクトを完遂することができました。
 私はガールスカウトでの活動期間があり、ベンチャー隊には2級スカウトで上進しました。そのため、はじめは富士スカウト章を目指そうと思ってもいませんでした。活動に積極的に取り組むうちに、自分の周りの人は自分が思っている以上に応援をしてくれているということが分かりました。ベンチャースカウトの皆さんの周りにも、応援してくれている人がたくさんいます。自分で限界を決めるのではなく、何事にも積極的に挑戦していってください。
私はガールスカウトでの活動期間があり、ベンチャー隊には2級スカウトで上進しました。そのため、はじめは富士スカウト章を目指そうと思ってもいませんでした。活動に積極的に取り組むうちに、自分の周りの人は自分が思っている以上に応援をしてくれているということが分かりました。ベンチャースカウトの皆さんの周りにも、応援してくれている人がたくさんいます。自分で限界を決めるのではなく、何事にも積極的に挑戦していってください。
プログラム委員会
ボーイスカウト日本連盟機関誌「SCOUTING」2022年1月号にも掲載している内容です