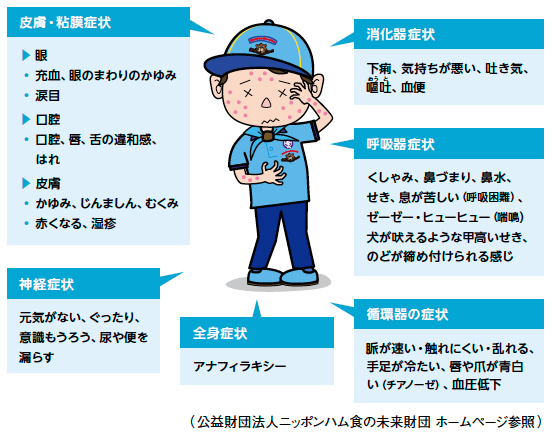 2. アレルギーを起こす人って?
遺伝的にアレルギー体質をもっている人といわれていますが、それ以外では、食生活の変化が大きく影響を与えています。主にインスタント食品やスナック菓子などの影響があり、次に、自律神経を乱す睡眠不足や不規則な生活、ストレスなどが原因といわれています。
3. アレルギー症状を軽くするために
規則正しい食生活を心がけましょう。暴飲暴食は避け、お酒や甘いものは控えめにしましょう。普段から栄養バランスの良い食事を心がけ、体に優しい野菜や緑茶をとるようにしましょう。そして、何よりも、アレルゲンを避けることが大切です。アレルギー性鼻炎であれば、マスクなどをして花粉やハウスダスト、ほこりを近づけないこと。食物アレルギーであれば、アレルゲンとなる食品をとらないことです。食品については、表示が義務づけられているので、必ず確認しましょう。
4. 予防対策
野外活動において安全を考えるうえで、次のことに注意しましょう。
2. アレルギーを起こす人って?
遺伝的にアレルギー体質をもっている人といわれていますが、それ以外では、食生活の変化が大きく影響を与えています。主にインスタント食品やスナック菓子などの影響があり、次に、自律神経を乱す睡眠不足や不規則な生活、ストレスなどが原因といわれています。
3. アレルギー症状を軽くするために
規則正しい食生活を心がけましょう。暴飲暴食は避け、お酒や甘いものは控えめにしましょう。普段から栄養バランスの良い食事を心がけ、体に優しい野菜や緑茶をとるようにしましょう。そして、何よりも、アレルゲンを避けることが大切です。アレルギー性鼻炎であれば、マスクなどをして花粉やハウスダスト、ほこりを近づけないこと。食物アレルギーであれば、アレルゲンとなる食品をとらないことです。食品については、表示が義務づけられているので、必ず確認しましょう。
4. 予防対策
野外活動において安全を考えるうえで、次のことに注意しましょう。
- 入隊時や活動前など、事前に活動参加者の健康調査を実施し、アレルギーの有無を確認しておくこと。 特に、食物アレルギーについては、アレルゲンの食材を特定しておくこと。
- 食物アレルギーの該当者がいる場合は、安全対策計画書の中で、献立や食材をチェックしておくこと。 また、代用食材(献立)を準備しておくこと。
- 自分たちで調理しない場合は、事前に、調理する人に食物アレルギーがあることを連絡しておくこと。
- 野外では、マスクをするなどして、体内にアレルゲンを侵入させないようにすること。
「セーフ・フロム・ハーム」・安全委員会 参考文献:大阪連盟『 新・野外活動の安全Q&A』
 卵
卵 乳
乳 小麦
小麦 えび
えび かに
かに そば
そば 落花生
落花生 あわび
あわび いか
いか いくら
いくら オレンジ
オレンジ カシューナッツ
カシューナッツ キウイフルーツ
キウイフルーツ 牛肉
牛肉 くるみ
くるみ ごま
ごま さけ
さけ さば
さば 大豆
大豆 鶏肉
鶏肉 バナナ
バナナ 豚肉
豚肉 まつたけ
まつたけ もも
もも やまいも
やまいも りんご
りんご ゼラチン
ゼラチンボーイスカウト日本連盟機関誌「SCOUTING」2020年3月号より














